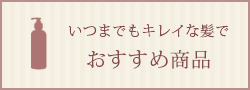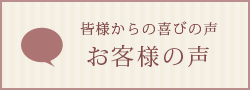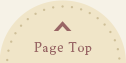こんにちは
豊橋・美容室「Ease villa」です
10月8日(火)骨と関節の日
「梨」について
梨はおいしいだけでなく、夏バテ解消の効果的です
梨は大きく分けて2種類、国内品質の和梨 =水分の多さと噛んだ時の食感とスッキリした味わい、西洋品種の洋ナシ
=水分の多さと噛んだ時の食感とスッキリした味わい、西洋品種の洋ナシ =濃厚で甘みが強く食感もねっとりとしている
=濃厚で甘みが強く食感もねっとりとしている
梨には、カリウムやアスパラギン酸、ポリフェノールなどの多くの栄養素があります
ソルビートル=果糖の一種、整腸作用があり、比較的に低カロリーで虫歯になりにくいが、量をたくさん摂ると下痢を起こすので注意が必要です
食物繊維=デトックス効果や体内への脂肪吸収を抑制する効果のあります
カリウム=血圧抑制、体内の余分な塩分の排出、解熱作用もあり、夏バテや夏風邪に最適
アスパラギン酸=体内のタンパク質合成やエネルギー代謝の促進など
タンニン・ポリフェノール=体内の抗酸化作用があり、生活習慣の予防にも役立つ
クエン酸=疲労回復に発揮
食べ方は、その、ままでもおいしいですが、サラダ・ジュースにしてもいいですね
梨には、プロテアーゼと言うタンパク質を分解してくれる消化酵素 が含まれているので、肉を食べた後に梨を食べたり、料理をする際、すりおろした梨の中に15分ほど肉に漬けておくと肉が柔らかくなります
が含まれているので、肉を食べた後に梨を食べたり、料理をする際、すりおろした梨の中に15分ほど肉に漬けておくと肉が柔らかくなります (パイナップルでも同じ効果が得られます)また、皮だけをミキサーにかけて、カレーの隠し味に入れてもいいですね
(パイナップルでも同じ効果が得られます)また、皮だけをミキサーにかけて、カレーの隠し味に入れてもいいですね
塩分を多くとる人 やストレスが多い人
やストレスが多い人 やアルコール・コーヒー・甘いものを良く摂るする人
やアルコール・コーヒー・甘いものを良く摂るする人 に、梨はお勧めです
に、梨はお勧めです

こんにちは
豊橋・美容室「Ease villa」です

10月6日(日)
シイタケについて
シイタケは生で食べるよりも、乾燥させる事で旨味と栄養もアップします
シイタケの栄養は、食物繊維、カリウム、ビタミンD、葉酸などたくさんの栄養素があり、低カロリーでダイエット、美容にもピッタリ
カルシウムの吸収を促すのがビタミンD ビタミンDには歯や骨を丈夫にしたり、脳神経の発達を促す作用もあります
ビタミンDには歯や骨を丈夫にしたり、脳神経の発達を促す作用もあります
カリウムが豊富なので、体内の水分バランスを調節してくれる栄養素 むくみの解消に効果的。食物繊維は腸内環境を整え、便秘解消、肌荒れ、ダイエットにも効果あり、葉酸が多く含まれているシイタケは、妊婦さんにも積極的に食べてほしい
むくみの解消に効果的。食物繊維は腸内環境を整え、便秘解消、肌荒れ、ダイエットにも効果あり、葉酸が多く含まれているシイタケは、妊婦さんにも積極的に食べてほしい 葉酸にはビタミンB群の一つで、細胞の生成や再生を助けてくれます。さらに、赤血球やDNA、核酸を作る働きもあるため、胎児の成長に欠かせない栄養素でも
葉酸にはビタミンB群の一つで、細胞の生成や再生を助けてくれます。さらに、赤血球やDNA、核酸を作る働きもあるため、胎児の成長に欠かせない栄養素でも
多糖類(βグルカン)には、免疫の活性力を高めて、ウイルスに対する抵抗力を上げる効果や癌の増殖を抑えたり弱らせたりする
骨の吸収を助けるビタミンDは、骨粗しょう症予防効果に効果があり、エリタデニンと言う成分も多く、血圧抑制効果、血管のつまりやコレステロールの増加を防ぐ効果がある。毎日食べ続けることで、血液サラサラ、アンチエイジング、生活習慣病予防に継続的に摂りたい食材の一つです
注意すべき点
干しシイタケは、プリン体を多く含みますので、食べ過ぎると尿酸値が上昇する可能性があります。痛風の症状をお持ちの方は食べ過ぎに注意しましょう 。
。
プリン体の1日に摂取上限は400MGとされ、この値を超える状態が続くと、高尿酸値血症と診断され、痛風、尿路結石、腎障害と言った様々な病気を引き起こすリスクもあります。何ごともホドホドが大切ですね

こんにちは
豊橋・美容室「Ease villa」です
10月5日(土)

今日は、「レジ袋ゼロデー」=ごみ減量のために、2002年に制定
今日は柿について
柿の栄養素は、ビタミンC・A・K・B1・B2などの天然の総合ビタミン剤と呼ばれる。中でもビタミンCはミカンの2倍もあるそうです
日本では昔から栽培されていたようで品種も1000種類以上あり、かつては、庭の柿の木がある家も多く、干し柿にすれば冬の間も食べられる身近な食材でした
ビタミンC=疲労回復・風邪予防 ビタミンA=免疫力を高める作用の他、二日酔いの回復効果があると言われる、柿の渋みの元になっているタンニンには、アルコールが成分を分解する力があり、カリウムには利尿作用があります。体内に蓄積されたアルコール成分はタンニンが分解し、カリウムが尿として体外へ排出してくれます
柿の葉にも、実に負けないくらいビタミンCが含まれており、ミカンの30倍と言われています。柿の葉を使った柿茶は有名ですが、柿の葉のビタミンCは熱してもそれほど崩れないので、お茶として飲むのもいいでしょう
柿の皮にも、カリウムやタンニンが含まれているので、て、二日酔いの朝には、柿を丸ごと食べて柿茶を飲むと効果的かもしれないですね
とは言え、何事も取り過ぎは禁物!食べ過ぎてしまうと身体を冷やしてしまい、消化不良になる場合もあり、また、タンニンを取り過ぎると貧血や便秘の症状が出てしまう場合もあります。1日1個~2個くらいがいいでしょう
柿の種類
次郎柿=種はほとんどなく、果肉の果汁は少なく固めでコリコリとした食感があり、酸味は感じられません。生産地は愛知・豊橋 が有名のようです
が有名のようです
富有柿=果肉の繊蜜でとろけるような柔らかさと甘みがあり、果汁が多いのが特徴。富有柿と次郎柿は柿の代表格ででよく比較されます。「富有はあごで食べ、次郎は歯で食べる」と言われます。生産は西日本で多く作られ、もっと多く作られるのは奈良県 です
です
筆柿=形が毛筆の筆先に似ている。不完全甘柿で、一本の木に甘い柿に混じって渋いものが一割ほど混じって成ります。種子が入ると渋みが抜け甘くなり、種子が入らないと渋みが残ります。生産地は愛知県幸田町 や西尾市
や西尾市 が全国的に有名
が全国的に有名
市田柿=小ぶりで渋柿。見た目は美味しそうな色ですが、生のままでは渋みが強く食べられません。市田 は干し柿で有名
は干し柿で有名
愛秋豊=果実がとても大きく見た目が映えることや種が無く果肉がしっとりして甘くおいしい。愛知県豊橋市 で育成したもの
で育成したもの
柿にも栄養素が沢山あります、これから、続々店頭に並び手軽に食べられる果実ですね

こんにちは
豊橋・美容室「Ease villa」です

10月4日(金)
今日は、世界動物の日=動物の生態を理解し、動物虐待等の問題を考え直す日




サツマイモ
加熱しても残るビタミンCが含まれ、風邪予防、疲労回復、肌荒れなど免疫力アップにも効果があります
食物繊維を効率よく摂取することが出来、便秘の改善(サツマイモの皮にも栄養と食物繊維があり、腸内環境を整えたい人は皮まで食べることをお勧めします)や、カリウムが豊富なのでナトリウムを排出する役割があり、高血圧の予防やむくみ防止に効果がります。また、皮にポリフェノール、カルシウム、ビタミンCなどが含まれているので、皮まで料理して栄養をたっぷりと摂りましょう
紫芋にはアントシアニンやポリフェノールも有り、がんや生活習慣病の原因にもなっている活性酸素を抑制する働きもあります
ビタミンEは抗酸化作用があり、体内の活性酸素を減らします。安納芋など果肉のオレンジ色をしているのはカロテンによるもの。カロテンは、体内に取り込まれると、必要に応じビタミンAに変換されたり、β-カロテンとしての働きもします。カロテンは活性酸素を排除する働きもあります。
イモの種類
紅あずま=スイートポテトなどのお菓子の材料に、ホクホクとした食感で甘みが強い
紅赤=栗きんときや焼き芋に、味や風味がいい
紅小町=焼き芋としても人気、長期間の貯蔵でも風味が安定
紫芋=ソフトクリームやチップスなどに、アントシアニンが豊富
安納芋=焼きもがおいしい、しっとりとした甘みが強い
鳴門金時=焼き芋や大学芋に、程よい甘み
五郎島金時=お菓子のような甘さ
黄金千賀(こがねせんが)=芋焼酎の原料
パープルスイートロード=青果用の紫芋、従来の紫芋より味が良い
サツマイモ 、ホクホクと美味しい
、ホクホクと美味しい お菓子としても、ご飯のおかず料理としても万能食材
お菓子としても、ご飯のおかず料理としても万能食材

こんにちは
豊橋・美容室「Ease villa」です
10月3日(木)
今日は「登山の日」だそうです。日本山岳会が1905年、10月に発足したこと。「10(と)3(ざん)」と語呂合わせから、山に登ることで、自然と触れ、自然の素晴らしさを知り、その恩恵に感謝する日

食欲の秋 にちなみ、食材について、第一弾は「栗」
にちなみ、食材について、第一弾は「栗」
栗は大きく分けて4つの種類があります
国内で一般的に売られている「ニホングリ」 =果実が大きく、風味がよいのが特徴
=果実が大きく、風味がよいのが特徴 やや甘みが少なく渋皮がはがれにくい
やや甘みが少なく渋皮がはがれにくい
天津甘栗でおなじみの「チュウゴクグリ」 =小さくて甘く、渋皮がむきやすいが、栗の害虫の被害を受けやすいので、日本では栽培されていません
=小さくて甘く、渋皮がむきやすいが、栗の害虫の被害を受けやすいので、日本では栽培されていません
マロングラッセなどに使う「ヨーロッパグリ」 =小ぶりながら渋皮がむきやすい、病気や害虫の被害が受けやすい
=小ぶりながら渋皮がむきやすい、病気や害虫の被害が受けやすい
日本ではあまり見かけない「アメリカグリ」 =果実の品質も良いが、菌類の被害により破滅されたと言われています
=果実の品質も良いが、菌類の被害により破滅されたと言われています
栗の選び方
果皮の張りと光沢があって、ずっしりと重みがあるもの。
栗の実は、鬼皮と言う硬い果皮と、渋皮と言う種皮に覆われています。果実は種子が発達したナッツの一種 栗はあまり保存が出来ないの、早目に食べるようにしましょう。保存するときには、ポリ袋に入れ、冷蔵庫のチルド室で数日間保存することが出来、甘みが増します
栗はあまり保存が出来ないの、早目に食べるようにしましょう。保存するときには、ポリ袋に入れ、冷蔵庫のチルド室で数日間保存することが出来、甘みが増します
栗の栄養素
カリウム=高血圧予防・むくみ予防 葉酸=貧血予防 食物繊維=便秘改善 ビタミンC=風邪予防・美容効果 ビタミンB1=疲労回復・ストレス緩和 ビタミンB2・ビタミンB6・タンニン=老化防止 そのほか、マグネシウム・リンなど、栗は栄養素が沢山あります
栗は栄養価も高いですが、カロリーも高いので、食べ過ぎには気を付けて下さい

こんにちは
豊橋・美容室「Ease villa」です
10月1日(火)
今日から10月 今年も3ヵ月となり残りの日々を張り切っていきます
今年も3ヵ月となり残りの日々を張り切っていきます

乾燥対策として、外側からのスキンケアが思い浮かぶと思いますが、健康な肌を作るためには、体内からの新陳代謝を活発にすることも大切です
睡眠=就寝から3時間で深く眠る事が出来れば、肌を回復させる成長ホルモンが沢山分泌されることが分かっています
睡眠の質を上げる3つのポイント
①就寝時に血糖値が下がっている 状態にする。就寝前にはた食べない
状態にする。就寝前にはた食べない
②寝る頃に体温が下がる ようにする。就寝1時間前に入浴する
ようにする。就寝1時間前に入浴する
③就寝前1時間はスマホ、テレビなどは避けて 。脳の覚醒させない
。脳の覚醒させない
運動=運動不足により体の代謝が悪くなると老廃物が溜まり血行が悪くなり、ターンオーバ乱れたり、ストレスが溜まると肌に必要なビタミンも消耗されます。ストレッチ・ウォーキングなどの軽い運動やストレス解消法も大切です
乾燥肌になりやすい習慣=糖分の多い菓子パン、清涼飲料水、カフェイン、冷たいものなどは代謝が悪くなりやすいので控えましょう
乾燥肌になりにくい習慣=朝食をとると一気に体温が上がり、一日中代謝の高い状態で過ごすことが出来ます
こんにちは
豊橋・美容室「Ease villa」です
9月30日(月)
今日で9月が最終日となりますね

大人になってからニキビの原因の一つが、乾燥によるバリア機能低下 です。角質に十分な潤いを維持しておくことが出来なくなり、水分量の低下した角質が積み重なって毛穴をふさぎやすくなり、脂質が少なくてもニキビが出来てしまう
です。角質に十分な潤いを維持しておくことが出来なくなり、水分量の低下した角質が積み重なって毛穴をふさぎやすくなり、脂質が少なくてもニキビが出来てしまう ことも有ります
ことも有ります
また、乾燥以外にも、ストレス、睡眠不足、生理周期の乱れと言ったものもバリア機能を低下させる要因にもなります
乾燥が気になったら、低刺激で保湿効果の高いスキンケアに切り替えて、お肌の保湿アップ を図ります
を図ります
クレンジングや洗顔なども、洗浄力の強いアイテムや熱いお湯での洗顔は控えて下さい
クレンジングは、お肌をこすり過ぎないように気を付けて、汚れを落とし、お湯の温度は、38℃~40℃くらいを使い、洗顔は、しっかりと泡立てて優しく洗い、洗顔後は、タオルで肌の水分を抑えるように拭き、すぐに保湿のあるスキンケアでしっかりと保護します
こんにちは
豊橋・美容室「Ease villa」です
9月26日(木)
乾燥肌のお手入れには、保湿だけが大切 !!だと思われるかもしれませんが、体の冷えも乾燥肌を悪化させる原因にもなります
!!だと思われるかもしれませんが、体の冷えも乾燥肌を悪化させる原因にもなります
体の冷えは、血行が悪くなって肌に栄養が行き渡らない証 !
!
乾燥対策には、体の外 からの保湿と、体の中
からの保湿と、体の中 からの栄養+体温アップの2つが大切です
からの栄養+体温アップの2つが大切です
洗顔は32℃前後のぬるま湯で、よく泡立て、優しく洗い流します
洗顔後はすぐに、保湿の高い基礎化粧品を使い、しっかりと補います
お顔のマッサージやフェースパックなど、週1~2回のスペシャルケアで老廃物を流します
お風呂の温度は、38℃~40℃のぬるま湯に15分 浸かり、あ風呂上りはすぐ保湿ケアしましょう
浸かり、あ風呂上りはすぐ保湿ケアしましょう
毎日のストレッチ・エクササイズなどで体を動かし、代謝アップし血行促進を図ります
もっと寒くなりますと、手首、足首、首、お腹、腰の5か所の部位を冷やさないように心がけましょう
足先は体の中で最も血行が悪い部分なので、足の甲、足の指、足の裏など、足全体を丁寧にマッサージすると、血行促進に

こんにちは
豊橋・美容室「Ease villa」です
9月23日(月)
今日で三連休が終わりましたが、如何過ごされましたか?
いい時間を過ごされた事と思います

肌乾燥には、何を食べたらいいの?
それは、タンパク質+必須脂肪酸+ビタミン類 も必要です
も必要です
タンパク質=細胞の原料となる=魚、肉、大豆など に多く含まています
に多く含まています
必須脂肪酸(オメガ3系、オメガ6系)=肌細胞の細胞膜を作る=オメガ3系はサバ・イワシなど の青みの魚、オメガ6系はコーン油・大豆油など
の青みの魚、オメガ6系はコーン油・大豆油など に多く含まれています
に多く含まれています
亜鉛=肌・髪の毛・爪などの健康を維持する=牡蠣・レバー・牛肉・卵・チーズなど に多く含まれています
に多く含まれています
ビタミンA=NMF(天然保湿因子)の生成を促したり皮膚・粘膜を正常な状態に保つ=レバー・ウナギ・禄黄色野菜・卵黄など に多く含まれています
に多く含まれています
ビタミンB2・ビタミンB6=肌の再生を促進したり、細胞の原料となるアミノ酸の吸収を助ける=VB2は牛レバー・豚肉・納豆など に含まれ、VB6はこんにゃく・マグロ・鳥レバーなど
に含まれ、VB6はこんにゃく・マグロ・鳥レバーなど に多く含まれています
に多く含まれています
ビタミンE=肌の血行促進、新陳代謝を促す=アーモンド・ナット類、アボガド・イワシ・イクラなど の魚介類
の魚介類
成人女性体重50㎏の方で、1日のタンパク質の摂取量は、約50g
 ほどになります
ほどになります
例‥卵1個(6.1g)、豚バラ肉100g(12.8g)、イワシ100g(19.2g)など
亜鉛は、日常不足することはほとんどありませんが、極端なダイエット をしたり、お酒を飲む人
をしたり、お酒を飲む人 は不足気味になりやすいので、レバー・卵などを食べましょう
は不足気味になりやすいので、レバー・卵などを食べましょう
野菜は、㏠350g必要です

![]() =水分の多さと噛んだ時の食感とスッキリした味わい、西洋品種の洋ナシ
=水分の多さと噛んだ時の食感とスッキリした味わい、西洋品種の洋ナシ![]() =濃厚で甘みが強く食感もねっとりとしている
=濃厚で甘みが強く食感もねっとりとしている が含まれているので、肉を食べた後に梨を食べたり、料理をする際、すりおろした梨の中に15分ほど肉に漬けておくと肉が柔らかくなります
が含まれているので、肉を食べた後に梨を食べたり、料理をする際、すりおろした梨の中に15分ほど肉に漬けておくと肉が柔らかくなります (パイナップルでも同じ効果が得られます)また、皮だけをミキサーにかけて、カレーの隠し味に入れてもいいですね
(パイナップルでも同じ効果が得られます)また、皮だけをミキサーにかけて、カレーの隠し味に入れてもいいですね やストレスが多い人
やストレスが多い人 やアルコール・コーヒー・甘いものを良く摂るする人
やアルコール・コーヒー・甘いものを良く摂るする人 に、梨はお勧めです
に、梨はお勧めです


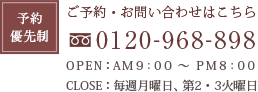

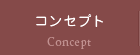
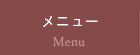


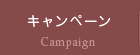
















 =
= 今年も3ヵ月となり残りの日々を張り切っていきます
今年も3ヵ月となり残りの日々を張り切っていきます 状態にする。就寝前にはた食べない
状態にする。就寝前にはた食べない

 には気温・湿度が低下
には気温・湿度が低下 の間に浴びた紫外線の影響で、「シミ、ソバカス、クスミ」が目立ち
の間に浴びた紫外線の影響で、「シミ、ソバカス、クスミ」が目立ち やすく、さらに、紫外線を浴び続けることで、コラーゲンなどにダメージを受け、皮脂膜が十分に作れなくなり、目元、口元なの「かさつき」気になり始めます
やすく、さらに、紫外線を浴び続けることで、コラーゲンなどにダメージを受け、皮脂膜が十分に作れなくなり、目元、口元なの「かさつき」気になり始めます
 の原因になることも
の原因になることも